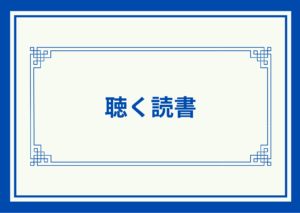あらすじ
長野県松本で暮らす作家のぼくは、連絡がとれない父・伊郷由史の安否を確認するため、新潟の実家へと戻った。生後3ヶ月で亡くなった双子の兄とぼくに、それぞれ〈文〉〈工〉と書いて同じタクミと読ませる名付けをした父。だが、実家で父の不在を確認したぼくは、タクミを名乗る自分そっくりな男の訪問を受ける。彼は育ての親を殺して死刑になってから、ここへ来たというのだが……神林長平、三十六年目の最新傑作にして、最大の野心作。
<出版社より>
2人のタクミを軸に自己とは、宗教とは、存在意義とは何かを問いかけている作品。
神林長平さんは長くこのテーマを扱っているように思う。【存在意義】ではなく【存在の証明】。
ここにいる自分は本当に自分なのか。何をもって証明するのか。その証拠は本当に揺らぎないものなのか。他者からの否定で簡単に崩れ去るものではないのか。SF作家ではあるんだけど、この方の書く作品はもはや哲学書だと思える。
一人称が実に見事に功を奏している作品ですね。急に視点が入れ替わり、どちらのタクミが主導権を握っているのか混乱します。そしてまさにその混乱こそが作者の訴えかけたいテーマなんです。
今ここにこうして立って話している自分は本当に自分なのか、この体と意識は繋がっているのか、この体を離れても意識は、自己は存在し続けるのか。
意識が個人の中に存在するわけではなく、他者とのかかわりの中に在るという考えは興味深かったですね。周りから固められていってドーナツみたいに中は穴が空いてるのでは?とか考えちゃいましたし、そうなってくると初めから自己なんてものは存在するのかとも。
クローンの考え方も実に面白かった。移植でもなく本体と別に作り上げるのでもなく、少しずつ内側からオリジナルと入れ替わっていく…。複製されていくのは身体だけなのか、それとも意識も複製されるのか。
前半はスローペース。でもこれが後半に効いてくる。まずはここでじっくり整理しながら読むんだけど、それでもなお後半混乱してきます。
読めば読むほど真実がわからなくなる。もはや真実すらあるのか。
神林さんの作品は内容もですが、文章がいい。言葉のチョイスも雰囲気も何もかもツボです。
この作品に限らず、この哲学的な内容を小説という枠組みに嵌め込んでくるのが何よりすごいと感じますね。
読後、心地よい疲労を感じられる作品です。